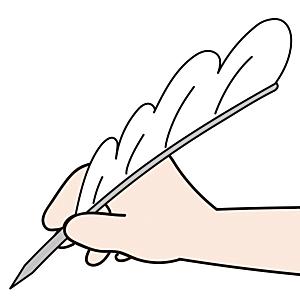1.遺言について
1) 遺言とは、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする意思表示のことです
遺言は、遺言者の死亡のときから効力を生じるのが原則です(985条1項)。(以下で、単に○○条とある場合は、民法の条文です)
例外的に、遺言者が停止条件付きの遺言をした場合には、その遺言の効果は遺言者の死亡後条件が成就したときに発生します(985条2項)。
遺言の無効原因として、民法で定める方式に違反した遺言(960条)、満15歳に達していない者がした遺言(961条)、2人以上の者が同一の証書でする遺言(共同遺言・975条)などがあります。
2) 遺言能力
民法は、遺言者が満15歳に達すれば遺言能力を有することになりますので、未成年者や制限能力者(成年被後見人、被保佐人、被補助人)であっても単独で遺言ができます(961条、962条)。
もっとも成年被後見人については、事理を弁識する能力を一時回復した時に、2人以上の医師の立会いのもとに遺言しなければならないという制限があります(973条1項)。
その場合、遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して署名・押印しなければならないことになっています(973条2項)。
ただし秘密証書遺言(後述)の場合は、遺言内容の秘密を保持する必要があるため、その封紙に上記の記載をし、署名し、押印しなければならないとされています(973条2項但書)。
2.遺言書の種類
遺言は、民法の定められた方式に従わなければならないことになっています(960条)。
方式に違反した遺言は、効力を生じませんので注意が必要です。
遺言の方式の種類を大きく分けると普通方式と特別方式があります。
普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります(967条本文)。
特別方式の遺言(967条但書)には、死亡危急時遺言(976条)、船舶遭難者遺言(979条)、伝染病隔離者遺言(977条、980条)、在船者遺言(978条、980条)の4種類があります。
遺言は上記のようにいくつかの種類がありますが、通常は普通方式による遺言で作成するのが原則です(967条)。
なぜなら、特別方式の遺言は、病気や遭難した船の中で死亡の危急に迫ったり、一般社会から交通の遮断された隔絶地にある(例:伝染病により隔離した病棟にいる)など、普通方式による遺言ができない特殊の事情のある場合に限って、普通方式の遺言よりも簡易な方式ですることが認められているからです。
また、特別方式による遺言がなされた場合であっても、遺言者が普通方式の遺言ができるようになったときから6ヶ月間生存する場合は、その効力を失います(983条)。
以下では、普通方式による遺言に絞り個別に説明します。
3.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者自身が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印するもので、遺言の中でも最も簡易にできる遺言です(968条)。
1) 長所と短所
長所:
- いつでも、どこでも簡単に作成できる
- 費用がほとんどかからない
- 内容を秘密にしておける
- 証人が不要である
短所:
- 方式不備で無効になったり内容が不完全で紛争が起きる危険性がある
- 偽造、変造のおそれがある
- 保管場所が分からず発見されなかったり、紛失や隠されたりするおそれがある
- 家庭裁判所の検認手続が必要で面倒(1004条)(後述参照)
2) 作成要件(968条1項)
ア. 遺言書の全文を自分で書くこと
イ. 遺言書を作成した日付も書くこと
ウ. 氏名も自分で書くこと
エ. 遺言書に自分で押印すること
アからエまでの4つの要件を1つでも欠いている場合は無効となります。
3) 相続開始後の検認手続
検認手続とは、後日における偽造又は変造を防止するために、家庭裁判所に遺言書の状態を確認してもらう手続です。
遺言書を保管する者または発見した者は、相続開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して検認を請求する必要があります(1004条1項)。
なお、検認手続において家庭裁判所は遺言書の現状を確定するのみで、遺言の有効無効については判断しません。
また、封印のしてある遺言書は、家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立ち会いがなければ開封することはできないことになっています(1004条3項)。
封印を方式としている秘密証書遺言のみならず、封印を方式としていない自筆証書遺言であっても封印されていれば、家庭裁判所外で開封してはいけないことになります。
検認の手続を怠った者、検認を得ないで遺言を執行した者、家庭裁判所外において遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます(1005条)。
4.公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人に対し遺言の趣旨を口授し、これを公証人が公正証書として作成する遺言です(969条)。
公正証書遺言は、公証役場で作成するのが原則ですが、病気などの場合には、公証人が自宅又は病院まで出張してもらって公正証書を作成してもらうことができます。
1) 長所と短所
長所:
- 公証人が作成するので証拠力が高く、また無効となるおそれがほとんどないため安全である
- 遺言書原本を公証人が保管するため(原本は公証役場で20年間保管)、偽造、変造、滅失、隠匿のおそれがない
- 字が書けない者でもできる
- 家庭裁判所の検認手続を要しない(1004条2項)
短所:
- 作成手続が複雑であり手間がかかる
- 公証人の手数料など費用がかかる
- 証人2人以上の立ち会いが必要
- 証人が必要なため秘密が漏れるおそれがある
2) 作成要件(969条)
ア. 証人2人以上の立会いがあること(1号)
イ. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(=口頭で述べること)すること(2号)
遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、手話通訳により「読み聞かせ」に代えることができる(969条の2第2項)。
ウ. 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させること
遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、手話通訳により「読み聞かせ」に代えることができる(969条の2第2項)。
エ. 遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印すること(4号本文)
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます(4号但書)
オ. 公証人が、その証書は方式にしたがって作成したものである旨を付記してこれに署名押印すること(5号)
3) 証人となることができない者
ア. 法律上の規定による証人欠格事由(974条)
- 未成年者(20歳未満の人。ただし婚姻していれば成年に達したものとみなされるので欠格者に該当しません(753条))(1号)
- 推定相続人、受遺者及びその配偶者ならびに直系血族(2号)
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人(3号)
イ. 事実上の証人欠格事由
- 遺言者の口授を理解できない者
- 筆記の正確なことを確認することができない者
- 署名することができない者
*目の見えない者について、判例は証人の欠格事由に該当しないとしています。
4.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にし、単に形式的な存在だけを公証人の関与によって確実にするものです(970条)。
遺言者の本文、日付、住所は、自書する必要はありませんので、ワープロ、パソコンでもよく、また他人に書いてもらったりすることもできるのが特徴です。
ただし、ワープロなどや、他人に書いてもらった場合など自書でない場合には、公証人及び証人の前で筆者の住所と氏名を述べることが必要です(遺言者自身が遺言書を書いた場合は、その旨を述べればよい)。
ワープロ・パソコン等を操作して遺言の作成を行った者の住所、氏名を述べず、「筆者」は自分であると申述したため、遺言が無効となった判例があります。
もっとも署名・押印は必ず遺言者自身がすることが必要です。
1) 長所と短所
長所:
- 遺言の内容の秘密が守れる
- ワープロ、代筆も認められる
短所:
- 手数料など費用が若干かかる
- 公証人が保管しないため、自筆証書遺言と同様偽造、変造、紛失、隠匿などのおそれがある字が書けない者でもできる
- 遺言内容そのものには公証人は関与していないため無効となるおそれがある
- 証人2人以上の立ち会いが必要
- 家庭裁判所の検認手続が必要で面倒(1004条)
2) 作成要件(970条1項)
ア. 遺言者がその証書に署名押印すること(1号)
イ. 遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章でこれに封印すること(2号)
ウ. 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること(3号)
口が聞けない者が秘密証書によって遺言をする場合は、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して「申述」に代えることができます(972条1項)。
エ. 公証人が、その証書を提出した日付け及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印すること(4号)
遺言者(=口が聞けない者)が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならず(972条2項)、封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載する必要があります(972条3項)。
3) 証人となることができない者
公正証書遺言で述べたことと同様です。
もっとも公正証書遺言と異なり、公証人は、遺言の内容を知ることができないので証人が欠格事由にあたるかまでは確認できないので、遺言者自身が注意して確認することが必要です。
4) 無効な秘密証書遺言の転換
秘密証書遺言の要件を欠いたため無効であった場合でも、自筆証書遺言の要件(遺言者が遺言の全文、日付、及び氏名を自書し、押印している)を満たしている場合には、自筆証書遺言として有効と認められています(971条)。
これは、遺言者の最終意思をできる限り尊重しようとする趣旨から無効行為の転換を認めているのです。
5) 相続開始後の検認手続
これは、自筆証書遺言で述べたことと同様です。
6.遺留分について
1) 遺留分とは、被相続人が、一定の相続人のために残さなくてはならない最低限度の財産の割合です
この遺留分を受けることのできるのは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人です(1028条)。
すなわち遺留分を受ける相続人の範囲は、被相続人の配偶者、子(その代襲者も含む)、直系尊属(両親など)に限られるということです。
2) 相続人の遺留分(1028条)
相続人の遺留分がどのくらいの割合で認められるかは、相続人が誰であるかによって変わってきます。そこで、それぞれの組み合わせについて見てみます。
ア. 第1順位の相続人の遺留分
- 子だけの場合
- 相続財産の1/2(2号)(子が数人いる場合は、1/2を等分する。例:子2人だと4分の1ずつになる)
- 配偶者と子の場合
- 相続財産の1/2(2号)(配偶者1/4、子1/4、子が数人いる場合は、1/4を等分する。例:子2人だと8分の1ずつになる)
イ. 第2順位の相続人の遺留分
- 直系尊属だけの場合
- 相続財産の1/3(1号)(父母両者ともいる場合は、6分の1ずつになる)
- 配偶者と直系尊属の場合
- 相続財産の1/2(2号)(配偶者1/3、父母1/6、父母両者ともいる場合は、12分の1ずつになる)
ウ. 第3順位の相続人の遺留分
- 配偶者だけの場合
- 相続財産の1/2(2号)
- 配偶者と兄弟姉妹の場合
- 相続財産の1/2(2号)(兄弟姉妹には遺留分はないので配偶者のみ1/2)
*遺留分と法定相続分と異なりますので混同しないようにしてください。
3) 遺留分減殺請求
ア. 遺留分権利者に保障されている遺留分を超えて、被相続人が生前に贈与したり、遺言で遺贈した場合は、遺留分の侵害となります
ただし遺留分の侵害があったからといって無効となりません。
遺留分を侵害された人が侵害された分を取り戻ししたい場合は、侵害されている分の請求をする必要があります(遺留分減殺請求)。
遺言者の死後に、相続人によって必ず遺留分減殺請求が起こるかどうかは実際に相続が始まってみないと分かりませんが、無用なトラブルを避ける意味で、遺留分に注意して遺言を残すように心がけたいものです。
イ. 遺留分減殺請求の仕方
遺留分減殺請求は、被相続人から贈与や遺贈を受けた者に対して意思表示をすれば足り、訴えによる必要はありません(1031条)。
しかし、意思表示の方法として確実に相手方に配達でき、しかも後日問題が起きた場合に証拠として残す意味で内容証明郵便で請求するのが望ましいといえます。
もっとも、遺留分減殺請求をする順序は、遺贈、最近(=相続開始前に近いもの)の贈与、古い贈与となります(1033条、1035条)。
これは、贈与は、相続開始前にすでに相続財産から逸失していることから、受け取った相手の利益を害しやすいのに対して、遺贈の場合は、それを受け取るほうも減殺請求を受けることを予測しやすいことからできるだけ遺贈を先にすることが望ましいという趣旨からです。
ウ. 遺留分減殺請求権の消滅時効
遺留分減殺権利者が、相続開始と贈与または遺贈により遺留分を侵害する事実を知ったときから1年間遺留分減殺請求権を行使しなかったときは時効により消滅します(1042条前段)。
また相続開始の時から10年を経過したときは、遺留分権利者が知っているか知らないかにかかわらず、遺留分減殺請求権は消滅します(1042条後段)。
エ. 具体例
遺留分の算定方法:
相続財産の総額 × 遺留分の割合 = 遺留分の額
↓ 次に
遺留分の額 - 実際に受けとった相続財産の価額 = 侵害された額
では、遺留分減殺請求のための遺留分算定方法を簡単な具体例で説明することにします。
設例:
被相続人の遺産総額が8,000万円で、相続人は妻、長男、次男がいたところ、愛人に5,000万円遺贈し、残った財産は各自法定相続分どおりに相続させるとの遺言が残されていた場合を考えます。
実際に受け取った額を見てみると
妻
3,000万円(便宜上残った財産を算定基準額とします) × 1/2(法定相続分) = 1,500万円
長男
3,000万円(便宜上残った財産を算定基準額とします) × 1/4(法定相続分) = 750万円
次男
3,000万円(便宜上残った財産を算定基準額とします) × 1/4(法定相続分) = 750万円
愛人
5,000万円
↓
次に各相続人の遺留分額を計算すると
妻の遺留分額
8,000万円(遺産総額) × 1/4(遺留分) = 2,000万円
長男の遺留分額
8,000万円(遺産総額) × 1/8(遺留分) = 1,000万円
次男の遺留分額
8,000万円(遺産総額) × 1/8(遺留分) = 1,000万円
↓
最後に各相続人の侵害された額を算定します
妻
2,000万円 - 1,500万円 = 500万円
長男
1,000万円 - 750万円 = 250万円
次男
1,000万円 - 750万円 = 250万円
上記のように妻500万円、長男250万円、次男250万円について遺留分を侵害されていますので、各自愛人に対し侵害された分を遺留分減殺請求により取戻請求をすることができます。